第1回 衝撃のクオーツ式時計の開発 それは長き戦いの始まりにすぎなかった
2011年10月

テレビやパソコン、腕時計などの中で静かに時を刻み続ける水晶デバイス。現在では「産業の塩」と称されるほど、エレクトロニクス業界に欠かせないデバイスへと成長した。エプソントヨコムは、その水晶デバイスのトップ・メーカーである。同社の事業の屋台骨を支えているのが、水晶材料にMEMS加工を施した独自技術「QMEMS」だ。この技術を駆使することで、これまで水晶デバイスの小型化と高性能化の両方を実現してきた。最先端技術であるQMEMSだが、その起源は1970年代前半までさかのぼる。30有余年のエンジニアたちの努力によって誕生したのがQMEMSである。このQMEMSストーリー“微の歴史”は、QMEMSの起源となる技術が生まれた当時の状況に始まり、QMEMSを生み出すべく苦闘したエンジニアたちの活躍を綴った物語である。第1回目は、世界初のクオーツ式腕時計が誕生した直後から、QMEMSの起源となる技術の開発前夜までを追った。
諏訪湖のほとりの企業が競争を制す
1969年、長野県の諏訪湖のほとりで世界を驚愕させる出来事が起こった。世界初のクオーツ式腕時計である「セイコー クオーツアストロン 35Q」の実用化に成功したのだ(図1)。
まさに、それは画期的だった。それまでのクオーツ式時計といえば、精度は極めて高いものの、壁掛け時計ほどの大きさがあり、手軽に持ち運ぶことはできなかった。もちろん、機械式の腕時計はすでに存在していたが、こちらは精度に問題があった。高精度化と小型化。この2つの課題を同時に解決すべく、世界中のさまざまな企業が1960年代の中盤から後半にかけてしのぎを削っていた。
この開発競争を制したのが、諏訪湖のほとりに社屋を構えていた諏訪精工舎(現在のセイコーエプソン)である。競合企業に先駆けて実用化できたポイントの1つは、水晶振動子の小型化にあった。従来の水晶振動子は、外形寸法が非常に大きく、腕時計に収めることは不可能だった(図2)。この問題を「音叉型」という新しい構造を採用することで解決した。開発した水晶振動子「Cal.35SQ用」*の外形寸法は、直径4.3mm×長さ18.5mm(図3)。さらに、腕に取り付けると常に振動や衝撃にさらされるという問題は、水晶振動子の内部構造を工夫することで乗り切った。
* 当時の音叉型水晶振動子は、社内で製造していた腕時計向けだった。このため、「製品型番は付けておらず、腕時計の動作機構であるムーブメントの名称(キャリバー、Cal.)で呼んでいた」(禰宜田六己)という。

図2:クオーツアストロン
開発前の水晶振動子
クオーツアストロンが登場する前に実用化されていた水晶振動子の例である。長さは約50mmもあった。これでも、当時の水晶振動子の中では小型品だった。

図3:クオーツアストロンに採用された音叉型水晶振動子
新規に開発した音叉構造を採用することなどで、直径4.3mm×長さ18.5mmへの小型化に成功した。型番は「Cal.35SQ用」。振動周波数は8.192kHzである。
世界初のクオーツ式腕時計の実用化と、音叉型水晶振動子の開発は、多くのエンジニアが流した汗と涙の結晶である。しかし、それは決して終わりではなかった。現在も続く、長い長い戦いの始まりにすぎなかった。
小型化の方法は分かっていた
エンジニアたちに休息のときはない。世界を驚かせたクオーツ式腕時計だったが、ひとたび実用化してしまえば、それが日常と化す。エンド・ユーザーは、もっともっと良いものを欲しがる。それは今も昔も変わらない。
クオーツアストロンを世に送り出した翌年の1970年には早くも、水晶振動子の開発チームにさらなる小型化の厳命が下った。目的は、商品性をより高めると同時に、耐衝撃性や量産性に優れたクオーツ式腕時計を開発することにあった。クオーツアストロンは、画期的な商品だったが外形寸法が若干大きかった。クオーツ式腕時計を普及させるには、さらなる小型化が不可欠と判断。しかし、クオーツ式腕時計を小型化するには、直径4.3mm×長さ18.5mmの水晶振動子(Cal.35SQ用)では大きすぎた。ムーブメント*に収めることができなかったのである。
* ムーブメントとは、時計の中に収められている動作機構のこと。
苦労に苦労を重ね、やっと実用化にこぎつけた小型の音叉型水晶振動子。普通であれば、「やっと、大変な開発が終わったところなのに・・・。そんな簡単に、さらなる小型化できるわけない」といった声が開発チームから上がっても不思議ではないところだ。しかし、開発チームから後ろ向きの発言は一切なかった。すぐさま行動を起こしたのだ。
その理由は何だったのだろうか。1972年から水晶デバイスの開発に携わった高田晴夫氏は、当時をこう回想する。「私自身はまだ、水晶振動子の開発にかかわっていなかったが、水晶振動子の開発チームは、小型化の方法を最初から分かっていた。音叉型水晶振動子を小型化するには、振動周波数を高めればいい。原理を考えれば、当たり前のことである」(同氏)。
クオーツアストロンで採用していた音叉型水晶振動子の振動周波数は8.192kHz。これを2倍に高めれば、長さは1/√2倍になる。つまり、16.384kHzに高めれば、長さが約0.7倍になる計算だ。振動周波数を高めること自体は難しくない。事実、1970年当時のクオーツ式置き時計には、振動周波数が100k~200kHzの水晶振動子、放送局の設備にはMHzオーダーの水晶振動子が使われていた。
方針は決まった。振動周波数を2倍にして、音叉型水晶振動子をひと回り小さくすればいい。そうすれば、間違いなく小型クオーツ式腕時計のムーブメントに収められるはずだ。意気揚々に作業に取りかかる開発チーム。しかしその直後に、1つの難題が開発チームに重くのしかかることになる。
半導体技術の進化が救う
難題とは、消費電力が増えてしまうことである。消費電力が増大すれば、腕時計の電池駆動時間が短くなる。電池交換が頻繁に必要なクオーツ式腕時計に商品性がないことなど自明の理だ。何とかして、消費電力を下げなければならない。
実は、「振動周波数を高めれば、消費電力が増大する」ことは、開発に着手する前から原理的に分かっていた。水晶振動子の消費電力は、振動周波数の2乗に比例して増える。つまり、振動周波数を2倍にすれば、消費電力は4倍になる。消費電力を削減することは一筋縄ではいかない。しかし、ほかに小型化する術(すべ)がなかったのだ。
開発チームは、途方に暮れた。「何かいい手はないか」。手詰まり感が漂い始めた1971年。海の向こうのアメリカから朗報が届いた。ある半導体メーカーが新しい半導体技術を開発したという一報である。
開発チームは、藁にも縋る(わらにもすがる)思いで、この一報に飛びついた。実際のところ、消費電力について、クオーツアストロンにメスを入れるとしたら、発振や分周といった機能を担う電子回路にあることは薄々気付いていた。クオーツアストロンに搭載していた電子回路は、バイポーラ・チップなどを組み合わせたハイブリッド回路である。これを新しい半導体技術に切り替えれば、消費電力を削減できるかもしれない。
担当者は、すぐさまアメリカに飛んだ。異国の地で目にしたものは、まったく新しい技術だった。
CMOS集積回路(IC:integrated circuits)という技術である。CMOS ICは、現在では当たり前の技術だが、当時は画期的な技術だった。バイポーラ・チップなどを組み合わせた従来のハイブリッド回路と比べると、消費電力を大幅に削減できる。「これしかない」。担当者はそう直感した。
その後の開発はトントン拍子に進んだ。もちろん採用するのは、新しい半導体技術である。技術評価にはそれなりの時間を費やした。しかし、開発を阻害するような大きな問題は発生しない。この結果、1971年のうちに振動周波数が16.384kHzで、外形寸法が直径4.3mm×長さ14.7mmと小さい音叉型水晶振動子「Cal.38用」の開発に成功した(図4)。

図4:音叉型水晶振動子「Cal.38用」
振動周波数を16.384kHzに高めることで小型化した。1971年に開発した。外形寸法は直径4.3mm×長さ14.7mmである。
次から次へと小型品を世に送り出す
電子デバイスの小型化に終わりはない。水晶デバイスとて同じだ。ひと回り小さくすれば、さらなる小型化が求められる。
次も、振動周波数を2倍に高めることで小型化を図った。1973年のことである。振動周波数は32.768kHzへと高まり、外形寸法は直径3.9mm×長さ10.9mmへと小型化された。こうして誕生したのが「Cal.57用」である(図5)。
もちろん、振動周波数が2倍に高まれば、消費電力は4倍に増える。この問題については、CMOS ICの改良に加えて、電池やモーターの性能向上などで解決した。
なお、32.768kHzという数字は、現在の時計用水晶振動子においてデファクト・スタンダード(事実上の標準規格)になっている振動周波数である。すなわち、時計用水晶振動子の高周波化はここで終わりを告げる。

図5:音叉型水晶振動子「Cal.57用」
振動周波数を「Cal.38用」の2倍に相当する32.768kHzに高めることで、外形寸法を直径3.9mm×長さ10.9mmに小型化した。1973年に開発した製品である。
さらに同じ年の1973年には、形状が円筒(シリンダ)型ではなく、フラット型の音叉型水晶振動子「F-001」を世に送り出す(図6)。外形寸法は5.1mm×12.1mm×2.4mmで、Cal.57用に比べると若干大きい。しかし、電子部品を載せるプリント基板への取り付け方(実装方法)が大幅に簡単になった。シリンダ型では、水晶振動子をプリント基板に立てるように取り付け、その後に金属端子を曲げて、プリント基板の上に寝かせるという作業が必要だった。フラット型であれば、プリント基板に差し込むだけで取り付けが完了する。
これが売れに売れた。普及タイプの小型腕時計や液晶ウオッチなどに相次いで採用されたからだ。例えば、液晶ウオッチでは、液晶パネルの下に電子回路を収めなければならない。こうした要求に、フラット型のF-001がもってこいだったわけだ。

図6:フラット型の音叉型水晶振動子「F-001」
「Cal.57用」と同様に、1973年に製品化した音叉型水晶振動子。従来の円筒(シリンダ)型ではなく、フラット型にすることで実装の容易性を高めた。外形寸法は5.1mm×12.1mm×2.4mm。振動周波数は32.768kHzである。
順風満帆に思われたが…
開発は、順風満帆に進んだ。エンジニアたちが思い描くストーリー通りに開発を進めることができたからだ。ビジネスも好調だった。1974年に入社した水晶デバイスのエンジニアである禰宜田六己は、「当時、諏訪精工舎は、時計用の音叉型水晶振動子において小型化の面でも、低コスト化の面でも、品ぞろえの面でも、競合他社を圧倒していた」と当時を振り返る。
開発も、ビジネスも、すべてが順調に進んでいると思われた。少なくとも、表面上は・・・。しかし、このときエンジニアたちは苦悩していた。そして、クオーツアストロンの開発からわずか5年後の1974年。遂に、その問題が顕在化することになる。
山下勝己(テクニカル・ライター)
(次回へ続く)
interview
 |
1963年に諏訪精工舎に入社。1972年ごろから、2000年に退社するまでの約28年間、水晶デバイスの開発に携わる。東京都の新宿で生まれ育った同氏が、諏訪精工舎に入社した理由は、「無類の電車好き」にある。「その当時、中央本線の甲府と上諏訪間が電化された。その電車にどうしても乗りたかったので、決まりかけていた航空機メーカーへの入社をあきらめ、諏訪精工舎を選んだ」(同氏)という。 |
 |
1974年当時諏訪精工舎の子会社であった松島工業(現在のセイコーエプソン伊那事業所)に入社。 入社直後から水晶デバイスの開発に従事しており、水晶デバイス開発暦は今年で37年となる。 現在(2011年9月)はTDBU製造技術部副主幹として後進の指導にあたる。 |
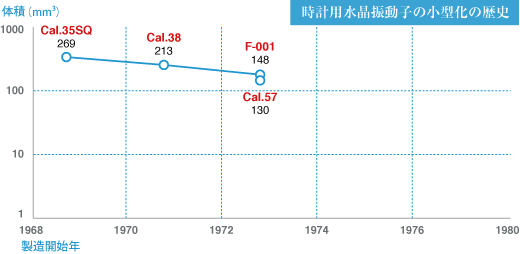
QMEMSはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

