第2回 QMEMSのルーツ、ここにあり フォトリソ導入が未来を切り開く
2011年12月

時が経つのは早い。世界を驚愕させたクオーツ式腕時計「セイコー クオーツアストロン35SQ」の製品化から5年。すでに、クオーツ式腕時計は、人々の生活に欠かせない道具となっていた。広く普及したクオーツ式腕時計。そのトップ・メーカーだった諏訪精工舎を待ち受けていたのは、激しい企業間競争だった。それまでの優位性を保つには、クオーツ式腕時計のさらなる小型化と低コスト化が不可欠。しかし、その心臓部にあたる音叉型水晶振動子の小型化と低コスト化は、そのときすでに限界に達していた。いかにして、この苦境を脱するのか。選んだ解決策は、まったく未知の技術の導入だった。第2回目は、QMEMSの起源(ルーツ)となる技術開発に取り組むエンジニアたちの活躍を綴る。
表向きは、確かに順調だった。しかし・・・
世界初のクオーツ式腕時計「セイコー クオーツアストロン35SQ」が誕生してから5年が経過した1974年。そのころにはクオーツ式腕時計の本格普及期を迎えて音叉型水晶振動子は増産に次ぐ増産を重ねていた。量産を担当していたのは、長野県の伊那に居を構える水晶デバイス部門(当時は松島工業)(図1)。「製造も、ビジネスも、何もかも順調。音叉型水晶振動子は、事業の柱として計算できそうだ」。伊那の地で働く人たちの多くは、満足感に浸っていた。
表向きは、確かに順調だった。しかし、開発の最前線で働くエンジニアたちに心休まる時間はなかった。この日も、諏訪の時計設計部門と伊那の水晶デバイス部門のエンジニアとの間で激しい議論が交わされていた。腕時計メーカーにとって、小型化と低コスト化は生命線。一息たりとも入れることはできなかったからだ。
「腕時計部門の要望は分かりました。でもこれ以上、音叉型水晶振動子は小型化できません」。
「いやいや、小型化してもらえなければ、次に製品化する女持ち(婦人用)の腕時計に入らない。何とかしてくれ」。

図1:長野県の伊那に居を構える水晶デバイス部門
1990年代のセイコーエプソン伊那事業所全景。3階建ての建物の後ろの平屋の大きな建物がフォトプロセス拡大のためにつくられた。
諏訪の時計設計部門には、絶対に引き下がれない理由があった。クオーツ式腕時計を世界で初めて市場に投入してから5年が経ち、市場での競争が次第に激しくなってきた。特に、香港勢の追い上げは急だった。それまでの優位性を保ち続けるには、さらなる小型化と低コスト化が不可欠。そこで検討していたのが、従来品に比べて大幅に小型化した婦人用クオーツ式腕時計の製品化だった。それには、心臓部にあたる音叉型水晶振動子の小型化が是が非でも必要だったのだ。
しかし、できないものは、できない。「もちろん、原理的には小型化できますが、そうするとコストが大きく跳ね上がってしまいます。だから事実上、これ以上の小型化は無理です」。これが水晶デバイス部門の本音だった。この日も、議論は平行線をたどるだけだった。
「諏訪男に、伊那女」
水晶デバイス部門のエンジニアたちは、腕時計の設計部門が置かれている窮状を痛いほど分かっていた。それだけに何とかしてあげたい。しかし、それに応える余裕はまったくなかった。音叉型水晶振動子の製造プロセスは、すでに限界に達していたからだ。
ここで、1974年当時の製造プロセスを簡単に説明しておこう。まずは、水晶ウェハから、音叉型(U字状)の水晶片を機械的な方法で切り出す。このため、この段階ではU字型の右側と左側の腕の長さや幅のばらつきが大きく、左右のバランスが確保できていない。そのばらつきは10µm以上もある。そこで、作業者がダイヤモンド・ホイールを使って1個1個の水晶片に対して腕の長さを調整し、20ppmの精度まで追い込んでいた。非常に細かく、根気がいる作業。この時点で、人間の力に頼った作業としてはほぼ限界に達していた。
こうした難しい作業を可能にしていたのは、細かな作業に長けた女性作業者の頑張りだった(図2)。長野県には「諏訪男に、伊那女」という言葉がある。勇壮な諏訪の男性と、優しくて辛抱強い伊那の女性が、理想的なカップルであることを意味する言葉である。これまでは何とか、この「伊那女」の頑張りで、しのいできた。
しかし、音叉型水晶振動子の度重なる小型化によって、ばらつきの影響が徐々に目立つようになってきた。以前よりも細かな調整が必要になるため、1個の音叉型水晶振動子の調整に掛かる時間が長くなる。もちろん、熟練した女性作業者であれば、比較的短い時間で作業できたが、そうした女性作業者をたやすく育成できない。製造に費やす時間が長くなれば、コストが上昇する。これまでは「伊那女」の頑張りで何とか問題を抑え込んできたが、クオーツ式腕時計の本格普及期を迎え、それだけに頼ることはできなくなってきた。
「じゃぁ、どうすればいいんだ」。
「問題を解決する上手い方法はないのか」。
その日の朝も、会議室では小型化と低コスト化を同時に実現できる製造方法を探し求めて、侃々諤々の議論が交わされていた。そのとき、あるエンジニアが口を開いた。「そろそろ、あの技術が使えるんじゃないか・・・」。

図2:音叉型水晶振動子の周波数調整工程
1970年代前半の音叉型水晶振動子の周波数調整工程。音叉型水晶振動子の先端を、ダイヤモンド・ホイールを使って手作業で削って周波数を調整している様子である。
「鶴の一声」で開発に着手
あの技術とは、1970年ごろから研究開発部門を中心に開発を進めていた「フォトリソグラフィ」である。フォトリソグラフィ技術とは、写真の露光技術を応用することで微細なパターンを作り込む技術のことだ。その当時すでに、集積回路(IC:integrated circuits)では欠かせない製造技術になっていた。
そのフォトリソグラフィ技術を、アメリカのStatek(ステーテック)という会社が水晶振動子の製造に適用することに世界で初めて成功した。それを聞きつけたのが、服部一郎(当時は諏訪精工舎 取締役)である。同氏は、すぐさまアメリカに飛んだ。そこで技術導入に関する話をまとめ、帰国後すぐに研究開発部門に対して、実用化に向けた技術開発を命じたのだ。
フォトリソグラフィ技術を水晶材料の加工に適用すれば、原理的に考えて加工精度を大幅に高められそうだ。「しかし、シリコンウェハ上の薄膜加工に使えても、果たして、水晶ウェハ自体の加工に適用できるのか・・・。適用できたとしても、期待通りの成果が得られるのか・・・」。正直なところ、こうした疑問を感じていたエンジニアも少なくなかった。
ただ、機械式の加工方法では、いずれ限界が訪れるのも明白だ。しかも、「新しいものに果敢にチャレンジするのが当時の諏訪精工舎の社風」(高田晴夫氏)。そこでプロジェクト・チームを立ち上げて、フォトリソグラフィ技術を利用した音叉型水晶振動子の開発に着手した。プロジェクト・チームの動きは速かった。すぐさま、アメリカから資料を取り寄せ、さらにはフォトリソグラフィの試作設備を導入して基礎実験を始めた。
フォトリソグラフィ技術は凄かった(図3)。エンジニアたちは、基礎実験を開始してすぐにポテンシャルの高さに驚嘆した。「基礎実験の段階で、加工精度が機械的な方法に比べて1けた高まることが確認できた」(禰宜田六己)からだ。フォトリソグラフィ技術であれば、機械的な加工方法の後継技術として使えそうだ。
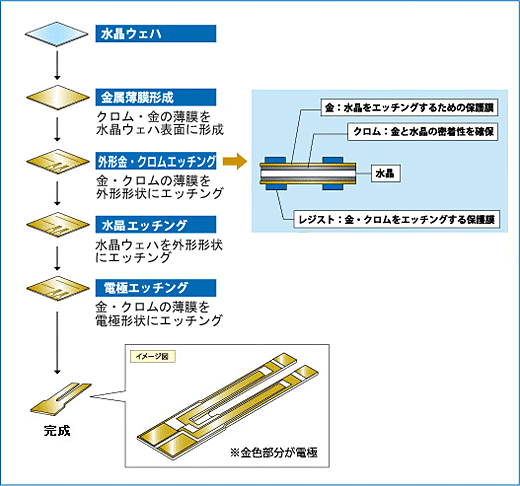
図3:フォトリソグラフィ技術のプロセス・フロー(当時)
写真の露光技術を利用することで、水晶ウェハから所望の形状の水晶片を抜き出したり、微細なパターンの電極を形成したりする。
ところが、である。Statek社のオリジナルのデバイス設計では、音叉型水晶振動子としての性能が出ない。電界効率が低いため、クリスタル・インピーダンス(CI値)*1が非常に高かったのだ。CI値が高いと、水晶振動子を発振させづらい。発振回路設計が難しくなる。「加工精度の高さは素晴らしいが、このままでは使えない」。これが、伊那の水晶デバイス部門で働くエンジニアが当初の試作品を評価した際の印象だった。
将来的な可能性は高いのは間違いない。しかし、今すぐは使えない。フォトリソグラフィ技術は、そういった烙印を押され、研究開発のステージへと戻っていった。
*1 水晶振動子の等価直列抵抗のこと。一般に水晶振動子は、コンデンサと抵抗を組み合わせた電気回路を使って発振させる。クリスタル・インピーダンス(CI値)が高いと、発振させるのが難しくなる。
独自技術でブレークスルー
それから、2年ちょっと。その間に、フォトリソグラフィ技術は大きなブレークスルーを果たしていた。それは、音叉型水晶振動子の新しい電極構造の開発である*2。
Statek社で開発されたオリジナルの電極構造では、電界効率が30%程度しか得られないためCI値が高い。そこで、プロジェクト・チームでは水晶材料のカット角*3を変更し、それに最適な電極構造を考案したのだ。この結果、電界効率を大幅に高めることに成功した。CI値については、機械的な加工方法で製造した音叉型水晶振動子に比べればまだ高かったものの、何とか使える数値まで下がっていた。「このレベルであれば、何とかなるはず」。そう考えていたエンジニアが、会議で「そろそろ、あの技術が使えるんじゃないか・・・」と発言したわけだ。
フォトリソグラフィ技術が抱えていたCI値が高いという課題。それをクリアできたのであれば、高い加工精度という特徴を存分に生かせるはず。多くのエンジニアがそう考えた。会議では満場一致で、フォトリソグラフィ技術の導入が決まった。
最大の課題を乗り越えたフォトリソグラフィ技術は、やはり凄かった。機械的な方法に比べて加工精度が1けた上回ることが、さまざまな波及効果を生んだ。1つは、水晶片のマウント方法である。従来の機械的な加工方法では、左右の腕の寸法にバラツキがあったため、振動漏れと呼ぶ成分が発生していた。これが外部に漏れると特性劣化を引き起こす。そこで、バネを使った複雑なマウント構造を採用して、振動漏れによる特性劣化を防いでいた。しかし、フォトリソグラフィ技術を導入したことで加工精度が高まり、左右の腕の寸法のバラツキが小さくなったため、バネを使う必要がない。気密封止用のリード端子に、水晶片を直接取り付けることが可能になったのだ。これが小型化とコスト低減に大きく貢献した。
もう1つは、周波数の調整方法である。従来は、ダイヤモンド・ホイールを使って作業員が1つ1つ調整していた。これでは、作業時間がかかりすぎる。しかし、フォトリソグラフィ技術の導入で加工精度が大幅に高まった結果、あとは微調整だけで済む。そこで、レーザーを使った薄膜トリミング法の採用が可能になった。この方法を使えば、周波数調整を自動化できる。生産性を大幅に高めることができるようになった。
*2 この技術の開発に対して、1982年の発明表彰において特許庁長官賞を受賞している。受賞者は、プロジェクト・チームの中心的な役割を担っていた小口紀久雄氏、下井明雄氏、芝田真氏、尾形俊昭氏の4名である。
*3 人工水晶の結晶構造は、三方晶系である。このため薄い水晶ウェハを切り出す際に、どの角度で切るかによって特性が違ってくる。
好事魔多し・・・

図4:フォトリソグラフィ技術で製造した最初の製品
1975年に製品化した「C-002」である。外形寸法は、直径2mm×長さ6mm。振動周波数は32.768kHzである。
フォトリソグラフィ技術の導入に加えて、その脇を固める新技術も開発された。万全な態勢が整った。そして遂に、1975年にフォトリソグラフィ技術を最初に適用した音叉型水晶振動子「C-002」の量産がスタートした(図4)。外形寸法は、直径2mm×長さ6mm。前世代品である「Cal.57用」の体積と比べると1/7と小さい(図5)。劇的な小型化に成功した。
コストについても、構造の簡素化と製造工程の革新で大幅に削減できた・・・はずだった。ところが、好事魔多し。製造現場では、1つの問題で苦しんでいた。製造歩留まりが極めて低いのだ。プロジェクト・チームの中でフォトリソグラフィの量産技術開発を担当していた禰宜田六己によると、「量産当初の歩留まりは10%程度だった」という。つまり、10個に9個は不良品だった。しかし、製品化したからには1カ月に5万個は生産しなければならない。「みんな休み返上で出勤し、何とか5万個の良品を確保していた」(禰宜田)。
こうしたスクランブル体制も1カ月程度であれば耐えられるだろう。しかし、長期間となれば無理な相談だ。次第に、水晶デバイス部門で働く人たちが疲弊していく。こうした状況を見かねて社内からは、「こんな技術で、本当に低コストで製造できるのか」「今までの機械的な加工方法の方が良かったのではないか」という声が上がりはじめた。「われわれの判断は間違っていたのか・・・」。水晶デバイス部門のエンジニアたちの心に、そんな思いがよぎり始めた。
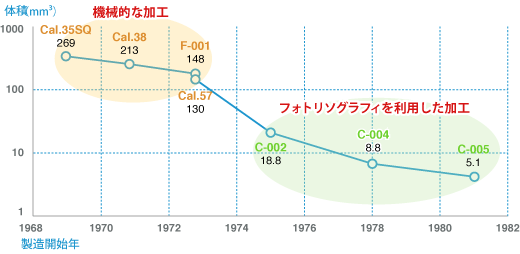
図5:音叉型水晶振動子の小型化の歴史
フォトリソグラフィ技術の導入で、大幅な小型化が可能になった。
本文では触れていないが、「C-002」以降は、1978年に直径1.5mm×長さ5mmの「C-004」、1981年に直径1.2mm×長さ4.6mmの「C-005」を製品化している。
趣味の木工が問題解決のヒントに
何とかして、この苦境を脱しなければならない。そのため、生産技術担当のエンジニアをリーダーとする歩留まり改善プロジェクト・チームが組織された。このチームに、若手エンジニアの禰宜田も組み込まれた。
このプロジェクト・チームが最初に着手したのは、歩留まり低下の原因究明である。不良品である音叉型水晶振動子の表面を顕微鏡で注意深くのぞいてみると、無数のピンホールが明いていた。水晶材料をエッチングした際に生じたものだ。なぜ、ピンポールが明いてしまったのか・・・。数週間にわたる調査の結果、水晶ウェハに付着した微少な汚れが原因であることを突き止めた。汚れの上に薄膜を形成した後にエッチングを施せば、その部分は密着性が低くなるため、ピンホールが明いてしまう。
そこで、水晶ウェハの扱い方や、洗浄方法などを工夫することで汚れを徹底的に排除することを試みた。この結果、水晶ウェハ上の汚れを十分に排除することに成功した。「これでもう大丈夫」。歩留まり改善プロジェクト・チームの面々は、胸をなで下ろした。
しかし、製造現場から歩留まり改善プロジェクト・チームの元に、思いも寄らない報告が届く。「歩留まりがあまり高まらないのですが・・・」という報告だった。どうやら、汚れに対する策は打ったものの、それだけでは不十分だったようだ。対策自体が甘かったのか。それとも別の原因があるのか。再び、不良品の表面を顕微鏡で調べてみた。確かに、ピンホールは明いている。「なぜだろうか」。今度は、原因がまったく分からなかった。歩留まり改善プロジェクト・チームでは、いろいろ試してみた。思い付くことは何でもやった。しかし、歩留まりは一向に高まらない。いたずらに時は過ぎていった。
そんな、ある休日のことである。禰宜田は、自宅で趣味の木工に没頭していた。木工では、荒れた板面の上に砥の粉(とのこ)を塗ってからニスなどを塗る。こうすると表面が綺麗に仕上がる。その作業をしているときにふと閃いた。「もしかしたら、水晶ウェハの表面も木材と同じように荒れているのではないか・・・」。確かに、その可能性はあった。水晶ウェハは、大きな人工水晶を機械的に切断し、研磨することで製造している(図6)。その際の応力によって表面層が荒れている可能性がある。
そこで禰宜田は、水晶ウェハの表面層を一度、エッチングですべて取り除いてから、薄膜を形成してみた。正解だった。ピンホールは一切できない。従来は、荒れている表面層の上にそのまま薄膜を形成していたため、ピンホールが明いていたのだ。
これで歩留まりは一気に上昇した。「もう休みに出勤することなく、十分な量を確保できる」。さらに、社内にくすぶっていたフォトリソグラフィ技術に対する否定的な意見も、歩留まりの上昇とともに、聞こえなくなっていった。
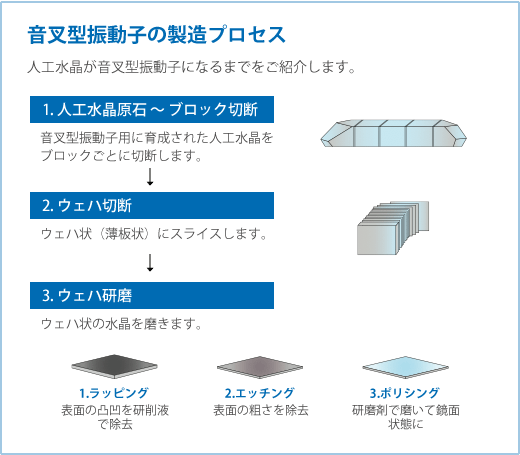
図6:人工水晶と水晶ウェハ
オートクレーブと呼ぶ専用装置で製造した人工水晶を機械的に切断することで、薄い水晶ウェハを製造する。
最後の難関も乗り越え、QMEMSの起源へ
従来の音叉型水晶振動子よりも体積が1/7と小さい上に、製造コストも低い。「こんな画期的なデバイスを、社内だけで使っていたのではもったいない。もっと多くの時計メーカーに使ってもらうため、外販しよう」という声が社内で高まってきた。そこで1976年に、「C-002」の外販を始めた。
「きっと、市場では大きな話題を集めるだろう」「世界中の顧客から、問い合わせが数多くあるはず」。伊那の水晶デバイス部門の胸は期待で膨らむ。実際にサンプル品を配布したところ、直径2mm×長さ6mmという形状に対する反応は極めて良かった。しかし、なかなか採用に至らない。その理由は、使いづらさにあった。
顧客の多くはそれまで、機械的な加工方法で製造した大型の音叉型水晶振動子を使っていた。それに比べると「C-002」はかなり発振させづらかったのだ。CI値をできる限り抑えたものの、従来の音叉型水晶振動子に比べればまだまだ高かった。社内の腕時計設計部門は、外形寸法を高く評価して採用してくれたが、社外の時計メーカーには使いづらさが高い障壁となり、採用してもらえなかったわけだ。
CI値が高くなる理由は、分かっていた。フォトリソグラフィ技術では光を利用して電極パターンを形成するため、水晶振動子の表面は加工できるが、側面は加工できない。光が当たらないからだ。このため水晶振動子の側面に電極を作り込むことができず、CI値が高くなっていたのだ。
デバイスの側面にも電極を形成するには、3次元のフォトリソグラフィ技術を確立する必要がある。これは、先行してフォトリソグラフィ技術を導入していたIC産業でも実用化されていない技術だった。この技術の開発を担当したのが禰宜田である。「最初は、とにかく顧客に使ってもらえるものを実現するため、水晶振動子の側面に電極を作り込む暫定的な方法を考案して量産を始めた。さらに、これと並行して開発を進め、1年以上の月日を掛けて、現在につながる恒久的な方法の確立に成功した。暫定的な方法は、歩留まりと作業効率の両面に問題があり、製造部門からはいつも叱られてばっかりだった」と禰宜田は当時を振り返る。
3次元のフォトリソグラフィ技術とは、どんなものか。残念ながら、この物語ではその詳細を説明できない。なぜならば、この技術は現在でも、エプソントヨコムの屋台骨を支えているからだ。約36年前に長野県の伊那で開発された「フォトリソグラフィ技術を使った音叉型水晶振動子の製造技術」。これが、「QMEMS」の起源(ルーツ)である。
山下勝己(テクニカル・ライター)
(次回へ続く)
interview
 |
1963年に諏訪精工舎に入社。1972年ごろから、2000年に退社するまでの約28年間、水晶デバイスの開発に携わる。東京都の新宿で生まれ育った同氏が、諏訪精工舎に入社した理由は、「無類の電車好き」にある。「その当時、中央本線の甲府と上諏訪間が電化された。その電車にどうしても乗りたかったので、決まりかけていた航空機メーカーへの入社をあきらめ、諏訪精工舎を選んだ」(同氏)という。 |
 |
1974年当時諏訪精工舎の子会社であった松島工業(現在のセイコーエプソン伊那事業所)に入社。 入社直後から水晶デバイスの開発に従事しており、水晶デバイス開発暦は今年で37年となる。 現在(2011年9月)はTDBU製造技術部副主幹として後進の指導にあたる。 |
QMEMSはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
