第4回 国内初の人工水晶の工業化 水晶デバイス・メーカーとしての躍進の転機に
2012年6月

2005年にセイコーエプソンの水晶デバイス部門と統合され「エプソントヨコム」となった東洋通信機。この会社の歴史はとても古い。前身の事業体は1891年に設立されており、その後、通信機の製造を生業に発展してきた。技術力は高く、同社が製造した無線機は、第2次世界大戦で使われた戦闘機「零戦」に採用されたほどだ。このように、もともとは通信機メーカーだった東洋通信機。しかし、1980~2000年代には、水晶デバイス・メーカーとしての知名度が上回ることになる。通信機メーカーから水晶デバイス・メーカーへ。そのきっかけとなったのは、「人工水晶の工業化」だ。今回は、人工水晶の工業化に国内で初めて成功したエンジニアたちの活躍を追った。
通信機器市場が急拡大
あの痛ましい戦争は、もう10年近くも前のことだった。行き交う人の顔には明るさが戻り、巷は好景気に沸いていた。後に言う「神武景気(じんむけいき)」である。
通信機メーカーである東洋通信機もご多分に漏れず、業績を大きく伸ばしていた。製品は、作る傍から飛ぶように売れていく。毎日がとても忙しい。しかし、従業員は泣き言一つ漏らさない。皆、充実感で満ちあふれていたからだ。
特に売れ行きが好調だったのが無線通信機である。電力会社に向けた短波帯無線電話機や、鉄道用携帯無線機、ロープウェイ用超短波無線機などの需要が急拡大していた。さらに、日本電信電話公社(現在のNTT)の中継機や交換機など、有線通信機も本格的な市場拡大期を迎えていた。「明るい未来が間違いなくやって来る」。従業員は皆、期待に胸を膨らませていた。
水晶が足らない
ところが、1954年(昭和29年)ころのことだ。そんな期待を一気に押しつぶしかねない問題が顕在化し始めた。「水晶材料が足らない」という問題である。
「水晶材料が足らないことが、どうして大きな問題なのか?」と疑問を持たれる方もいるだろう。実は、水晶材料は、無線通信機や有線通信機にとって極めて重要な役割を果たしていた。水晶材料を使って製造した水晶振動子は、非常に安定した周波数信号を生成できる。通信機は、この周波数信号を使って相手と情報をやり取りする。水晶振動子がなければ、通信機は動かない。つまり、通信機にとって水晶振動子は、「心臓部」の役割を果たしていたのだ。それは、今も昔も変わらない。
その水晶振動子だが、そもそも終戦直後の時期から品不足気味の状況にあった。理由は、天然の水晶材料(天然水晶)を加工して利用したからである。もちろん、日本国内でもある程度の量の天然水晶を採掘できる。しかし、含有不純物が少なく、双晶(互いに対称な二つの結晶が結合したもので、水晶デバイスには使えない)が一切ない良質な大型品はなかなか採れない。当時、こうした大型品を採掘できるのはブラジルに限られていた。
しかし、そのブラジルでも、良質な大型品を入手することは困難を極めた。水晶材料は、非常に重要な軍需物資だったからだ。東洋通信機で人工水晶の開発に携わり、現在は東京工科大学の応用生物学部で講師を務める永井邦彦氏によると、「良質で大きな天然水晶を採掘できる鉱山は、そのほとんどを米軍が管理していた。それでも、日本からブラジルまで買い付けに出掛けて、何とか必要な天然水晶を確保していた」という。
需要が比較的少ない時期であれば、こうした急場しのぎの対応でも何とか乗り切ることができた。しかし、歴史的な好景気をバックに、需要は急拡大している。もう、急場しのぎでは対応できなくなってきた。水晶材料がなければ、無線通信機は製造できない。「水晶材料が足らない」という問題は、東洋通信機にとってまさに死活問題だった。
甲府へと向かう
いかにして、この難局を乗り越えればいいのか。東洋通信機の川崎事業所では、来る日も来る日も深夜まで会議が続いた。しかし、数々の会議を経るにしたがい、意見は一つの方向へと収斂していった。「大型の天然水晶を確保できないのであれば、人工的に作るしかない」という方向である(図1)。
もちろん、反対意見はあった。「本当に、高品質な水晶を製造できるのか」「しかも大型のものが作れるのか」といった疑問があったからだ。だからといって、それ以上の可能性を秘めた代案は見つからない。「原理的には、間違いなく実現可能なはず。人工水晶の製造を実現させ、この難局を乗り越えよう」。こうして、人工水晶の製造に関する研究に着手することになった。
しかし、東洋通信機は通信機メーカーである。通信機に使う水晶振動子を製造する技術力には自信を持っていたが、人工水晶を製造する技術の開発についてはほぼゼロから出発する必要があった。だが、試行錯誤を重ねる時間的な猶予は一切ない。短期間のうちに開発するには、研究機関の力を借りなければならない。それならば、どの研究機関と組むべきか・・・。
そんな議論に明け暮れていたときだ。新聞に「山梨大学、人工水晶の合成に成功」という記事が掲載された。まさに「ナイス・タイミング」だった。東洋通信機の古賀氏と福永氏の両名は、すぐさま山梨県甲府市にある山梨大学に向かった。応対してくれたのは、同大学の国富稔教授、滝貞夫助手、浅原準平助手だった。

図1:人工水晶
現在、セイコーエプソンで製造している人工水晶の例である。今となっては、完全に透明で外形寸法が大きな人工水晶を育成できるようになっているが、開発当初は非常に小さく、色がついているものしか作れなかった。
生まれて初めて見たオートクレーブ

図2:山梨大学のオートクレーブ
写真左は、山梨大学に現存する最も古いオートクレーブである。このオートクレーブが作成された時期は不明。外形寸法は、内径30mm程度、深さ510mmである。現在でも、公開講座などで実際に人工水晶を育成している。写真右は、同大学 クリスタル科学研究センター(旧無機合成研究施設)の地下である。かつて、ここに大型の実験用オートクレーブが設置されていた。
(協力:山梨大学 教授の熊田伸弘氏)
山梨大学がある甲府市の北部には、天然水晶の産地である昇仙峡がある。このため山梨県内には、宝石の研磨や宝飾品の製造を行う企業が数多く存在していた。こうした地元産業の発展に寄与すべく、国富教授を中心とする研究グループは、1953年(昭和28年)に人工水晶の製造に関する研究に着手した。そして翌年の1954年(昭和29年)に、同大学の屋上に据え付けた小型オートクレーブ(人工水晶を成長させる高温高圧炉)で、日本初の人工水晶の製造を成功させた(図2)。古賀氏と福永氏が見たのは、この研究成果に関する新聞記事だった。
国富教授は、二人を暖かく迎え入れてくれた。そして、人工水晶の製造方法などを詳しく説明した後に、実験用のオートクレーブを披露したのだ。 オートクレーブの大きさは、内径が35mmで深さが500mm。現在のオートクレーブに比べれば、極めて小さい。しかし、二人は生まれて初めてオートクレーブという装置を目にした。古賀氏は、「ひどく感銘を受けた」と当時を述懐している*1)。
1)参考文献
東洋通信機、『トヨコムものがたり』、pp.60-66、平成2年3月15日発行
川崎に戻った二人は、湊才次郎社長や技術担当者などを交えた会議を開く。山梨大学で見聞きしたことをすべて報告。それを聞いた会議参加者に、異論はなかった。その場で、山梨大学と共同研究することが決議され、1955年(昭和30年)初頭に研究活動がスタートした。
夜も眠れない
最初に着手したのは、新しいオートクレーブの製作である。人工水晶を工業化するには、山梨大学の実験用オートクレーブでは小さすぎた。オートクレーブが小さければ、出来上がった人工水晶も小さくなる。一つの人工水晶からわずかな個数の水晶振動子しか製造できないため、コスト(単価)が極めて高くなってしまう。コストを下げて、工業化を実現するには、もっともっと大きなオートクレーブが必要だった。
そこで東洋通信機では、山梨大学の国富教授らの力を借りて、オートクレーブの大型化に取り組んだ。最初に製作したオートクレーブは、内径50mm×深さ800mmである。その次は、内径70~80mm×深さ1500~1600mmとさら一回り大きなオートクレーブ。そして1957年には、内径120mm×深さ2000mmと大きいオートクレーブの製作に成功した。
しかし、オートクレーブができたからといって、大型の人工水晶が簡単で製造できるようになるわけではない。含有不純物が少なく、結晶欠陥のない人工水晶はなかなか製造できない。育成条件を最適化したり、オートクレーブの構造をカスタマイズしたりといった細かな調整が不可欠だからだ(図3)。
さらに、不安定な電力事情がエンジニアたちの頭を悩ませた。当時の電力は現在のように安定しておらず、電圧が比較的大きく変動していた。このため、機械式の自動温度調整器が頻繁に誤動作したり、壊れたりしたのだ。オートクレーブ内部の温度が1℃下がっただけで、人工水晶の内部に不連続な領域が発生してしまい、結晶の品質が大きく低下してしまう。人工水晶を成長させるには、当時の小型品でも、種となる水晶を入れてから1〜2カ月かかる。ほんの短い時間でも温度が下がってしまえば、1〜2カ月の仕事が無駄になる。そのため、オートクレーブは四六時中、監視する必要があった。「人工水晶を成長させているときは、寝袋で仮眠を取りながら、夜中も監視することが多かった。監視できないときは、守衛さんにお願いし、何かあれば連絡してもらうようにお願いした。このため、盆や暮れには、守衛さんのところに、感謝の印としてお酒を持っていったものだ」(永井氏)。

図3:開発当時の様子
1950年代後半から1960年代前半のオートクレーブ開発の様子である。作成したオートクレーブを使って試作した人工水晶を引き上げているところ。
ついに工業化へ
こうした苦労を乗り越えて、1959年(昭和34年)には、比較的大きな人工水晶を製造できるようになり、やっと人工水晶の工業化にメドが立った。残るハードルは、オートクレーブの本数を増やすことである。本数が増えれば、人工水晶の量産性を高められ、多くの水晶振動子を製造できるようになるからだ。1959年年初の時点では、内径120mm×深さ2000mmのオートクレーブが2本しかなかった。
そんなとき、朗報が入った。1959年6月に、理化学研究所(後の新技術開発事業団)の工業化委託第1号のテーマとして、「人工水晶製造の工業化」が選ばれたのだ。これにより、2本のオートクレーブと、それに必要な制御装置を調達する資金を確保することに成功した。このほか、東洋通信機は自社費用で5本のオートクレーブを製作。これでオートクレーブの合計本数は9本に達した。このほか、電源(電圧)を安定化させるために、川崎事業所内に電源装置を設置し、高品質の人工水晶を製造する環境を整えた。

図4:量産当初にオートクレーブから引き上げた人工水晶
1966年ごろの様子である。写真右端が永井邦彦氏である。
「これで行ける」。水晶振動子の製造用としては、十分な量を確保できるようになった。これを受けて、ついに待ちに待った量産が始まった。つまり、国内初の人工水晶の工業化に成功したわけだ(図4)。
この話題は、各新聞紙上を賑わせることになる。それを受けて、競合企業も人工水晶の開発に着手した。山梨大学と一緒にほぼゼロからスタートし、何年も苦労を重ねてたどり着いた「人工水晶の工業化」である。この優位な立場を可能な限り、確保し続けたい。それには、常に新しい技術を次から次へと生み出す必要がある。そこで、東洋通信機は手を打った。山梨大学から滝貞夫氏(当時は助教授)を、さらに工業技術院電気試験所に就職していた浅原準平氏を獲得したのだ。こうして国内最高クラスの頭脳を手に入れ、技術開発体制を強化した。
こんなもの使えない
人工水晶の工業化に成功した以降は、結晶品質の向上とオートクレーブの大型化との格闘の歴史と言える。特に、工業化当初に苦戦したのは、人工水晶の結晶品質である。「水晶振動子の製造部門に持って行っても、『こんなもの使えない』と言われる始末だった」(永井氏)という。もっとも、天然水晶はほとんど入手できない。このため水晶振動子の製造部門は、歩留まりが低下するものの、不承不承ながらも人工水晶を使っていた。
人工水晶が使いづらい理由は、結晶品質が劣っていた点にあった。もちろん、結晶欠陥が入っていれば、そこを取り除き、比較的品質が高い部分だけを納品すればいい。見た目は、天然水晶とほぼ同じ。しかし、水晶の最大の特徴と言える「3次の温度特性(温度と周波数変動量の関係が3次関数になる特性)」が十分に現れない。これでは、高性能な水晶振動子を製造できなかった。
原因は、結晶の緻密さにあった。製造した人工水晶を詳しく調べると、結晶格子の大きさが天然水晶と違っていた。人工水晶の方が大きく広がっており、そこに不純物が入っていたのである。見た目では分からないミクロの世界での違い。それだけに、問題解決には困難を極めた。
あきらめていた材料で賭に出る
解決のポイントは、オートクレーブ内に満たす溶液にあった。当初は、米国企業などが採用していた炭酸ナトリウム(炭酸ソーダ)を使っていた。この溶液を使えば、オートクレーブ内の温度と圧力を低く抑えられる上に、育成速度を高められる。その分だけ、コストを抑えられるわけだ。しかし、この溶液では、天然水晶と同等の結晶品質が得られない。
実は、溶液の候補はもう一つあった。水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)である。ただし、この溶液を使って人工水晶を製造する場合は、オートクレーブ内の温度と圧力をかなり高くしなければならない。しかも、育成速度がかなり低い。デメリットが非常に多いため、当時は実用化をあきらめられていた材料だったのだ。
しかし、それまでの経験から炭酸ナトリウムでは十分な結晶品質が得られないことは明白だった。そこで、東洋通信機は賭に出た。炭酸ナトリウムと並行して、水酸化ナトリウムを使った人工水晶の量産にも着手したのだ。当初は、両者の結晶品質の間にあまり差はなかった。実際に、「1965年(昭和40年)ごろまでは、両方の溶液を使って人工水晶を生産していた」(永井氏)という。しかし、製造方法の最適化を進めるうちに徐々に差が現れる。そして、1970年(昭和45年)ころには、その差は歴然となった。水酸化ナトリウムを使い、育成条件を最適化したり、オートクレーブの構造をカスタマイズしたりしたことで、天然水晶に限りなく近い結晶品質の人工水晶が製造できるようになったのだ。永井氏は、「当時、高品質な人工水晶開発の陣頭指揮をとっていた浅原準平さんは、『製造現場がすぐ横にあって、日々、厳しい指摘を受けてきたからこそ良いものができたんだ』とよく言っていた」と当時を振り返る。
結晶品質が高まるやいなや、外販数量が急速に伸びていった。「天然水晶と同等の結晶品質の人工水晶がある」と目を付けたのは、欧州の通信機メーカーである。東洋通信機は、これらの企業と次々に大口契約を結ぶ。こうして、人工水晶は大きなビジネスへと育っていった。
世界有数の人工水晶メーカーに
最後に、オートクレーブの大型化にも言及しておこう(図5)。
人工水晶の工業化は、内径120mm×深さ2000mmのオートクレーブでスタートを切った。その後は、製造コストの削減を目的に、大型化が急ピッチで進む。1963年(昭和38年)には内径180mm×深さ3000mmのオートクレーブを導入した。東洋通信機では「A型」と呼ぶ。
そして1965年(昭和40年)には早くも、内径300mm×深さ5000mmの「B型」と呼ぶオートクレーブを開発し、同社の相模工場(神奈川県寒川町)に2基設置した。このオートクレーブは当時、「世界最大規模」を誇るものであり、人工水晶の大幅なコスト削減に寄与した。
1973年(昭和48年)には、内径400mm×深さ8000mmの「C型」と呼ぶオートクレーブを開発し、保原工場(福島県、現在は工場自体が廃止されている)に導入。1984年(昭和59年)には、内径650mm×深さ14000mmの「E型」のオートクレーブを宮崎東洋通信機に設置した。
東洋通信機は、こうした積極的なオートクレーブの大型化によって、世界有数の人工水晶メーカーへと成長した。さらに、人工水晶での経験は、さまざまな水晶デバイスを開発する推進役としても機能した。その後同社は、携帯電話機やカーナビ、ノート・パソコンなどに不可欠な水晶デバイスを次から次へと市場に送り出す。つまり、「情報化時代の幕開け」に大きく貢献することになる。
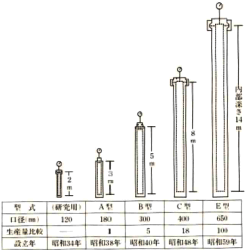
図5:オートクレーブ大型化の歴史
現在、セイコーエプソンで製造している人工水晶の例である。今となっては、完全に透明で外形寸法が大きな人工水晶を育成できるようになっているが、開発当初は非常に小さく、色がついているものしか作れなかった。
山下勝己(テクニカル・ライター)
(次回に続く)
人工水晶の作り方
人工水晶は、オートクレーブと呼ばれる超高圧の圧力容器を使って製造する。このオートクレーブは円筒状であり、高さは3階建ての建物とほぼ同じと大きい。この内部を約360℃、1100~1700気圧の環境に保つことで、2〜6カ月の月日をかけて人工水晶を成長させる。この方法を、水熱合成法と呼ぶ。 製造方法を具体的に説明しよう(図A)。まずは、天然水晶のかけら「ラスカ」を洗浄して乾燥させ、オートクレーブ下部の溶解域に入れる。上半分の成長域には、人工水晶を短冊状に切断した種水晶を吊し、水酸化ナトリウムや炭酸ナトリウムなどのアルカリ水溶液で容器内の80%ほどを満たす。これで準備完了だ。オートクレーブをトップカバーとクランプで密閉し、加熱することで、容器内部を高温高圧に保つ。すると、容器の内部では、ラスカがアルカリ水溶液に溶けて、SiO2の飽和溶液になる。オートクレーブの上半分(成長域)の温度は、下半分(溶解域)の温度よりも低く設定してあるので、自然対流が発生している。このため、下半分の飽和溶液が上部に移動して冷やされることで過飽和となり、種水晶にSiO2が付着して大きくなる。この状態を2~6カ月間維持することで、大型の人工水晶を成長させる。
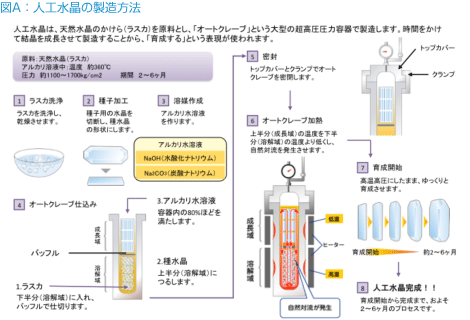
interview
 |
1965年に東洋通信機に入社。人工水晶の開発を担当した。開発の初期段階から、拡販段階、成熟段階までの長期間、人工水晶事業に携わった。定年後、トヨコム・エンジニアリングにて、新しい結晶材料の開発に取り組んだ後、東京工科大学 応用生物学部の講師に就任した。現在は、バイオ技術を利用した血液センサーの研究に取り組む一方、次世代の人材教育にも力を入れている。 |
 |
1972年に東洋通信機に入社。水晶発振器の開発や設計を担当した。その後、温度補償回路付き水晶発振器(TCXO)やFM変調器、デジタル方式のTCXOなどの開発を手掛ける。1年半の米国駐在後、モジュール品の開発や設計に携わった。現在は、電子デバイス商社の丸文に勤務。趣味はスキー、ゴルフ、クラシック音楽鑑賞。 |
 |
1977年に東洋通信機に入社。入社後は、水晶フィルタ(MCF:Monolithic Crystal Filter) の開発や設計を担当。その後、研究開発部門に異動し、SAW(弾性表面波)フィルタの開発に取り組む。現在は、セイコーエプソン デバイス管理部に在籍。趣味はスキー、ランニング、釣りなど。 |
QMEMSはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
